本記事のポイント
■ 大卒ニートが増える要因
■ 高学歴ニートは能力自体は高い
■ 精神的なケアが優先されるケースも
■ 高学歴ニートからの脱出方法とは?
言葉の定義
本記事では、高学歴ニートの定義として、「旧帝大や早慶をはじめとする有名大学卒」として考えます。

個人的には、高学歴ニートは一過性のものであることが多いと思います。そもそもニートと一括りにせず、ケアが必要な状態か否かを見分ける必要があると考えています。
私の周囲にも(旧帝大)、いわゆる「高学歴ニート」と呼ばれる人がいました。
でも、多くの場合、あまり周囲が気にするほどでもなく、社会復帰する人が大多数だと思います。
中には大出世を遂げた人も知っています。
ただし、ケース・バイ・ケースな部分もあります。
本記事では、高学歴ニートを生み出す原因や対策方法について、まとめてみます。
大卒ニート問題の現状把握
そもそも社会全体としてニートの母数はどのようになっているのか。
また、なぜ「高学歴ニートが増えた」と言われるのでしょうか。
まずは、大学卒のニートがどの程度いるのか見てみましょう。
- 本章の参考文献
- ・労働政策研究研修機構(JILPT) 資料シリーズNo.217
https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2019/documents/217_03.pdf
・青少年雇用対策基本方針 厚生労働省告示第百十四号
https://www.mhlw.go.jp/content/11804000/000759745.pdf
倍増したニートの大卒率
以下は、厚生労働省が所管する独立行政法人労働政策研究・研修機構のデータです。
2017年の調査によると、中卒が18.1%、高卒が57.2%、短大・専門学校卒が10.9%、大学・大学院卒が13.2%となっています。
| 中学卒 | 高校卒 | 短大・専門卒 | 大学・大学院卒 | |
|---|---|---|---|---|
| 全体 | 18.1% | 57.2% | 10.9% | 13.2% |
| 男性 | 18.8% | 57.9% | 7.8% | 14.7% |
| 女性 | 17.0% | 56.0% | 15.8% | 10.8% |
最近、なぜ「高学歴ニートが増えた」と言われるか。それは以下のグラフを見るとよくわかります。
つまり、1990年代と比べて大卒の割合が増えているのです。

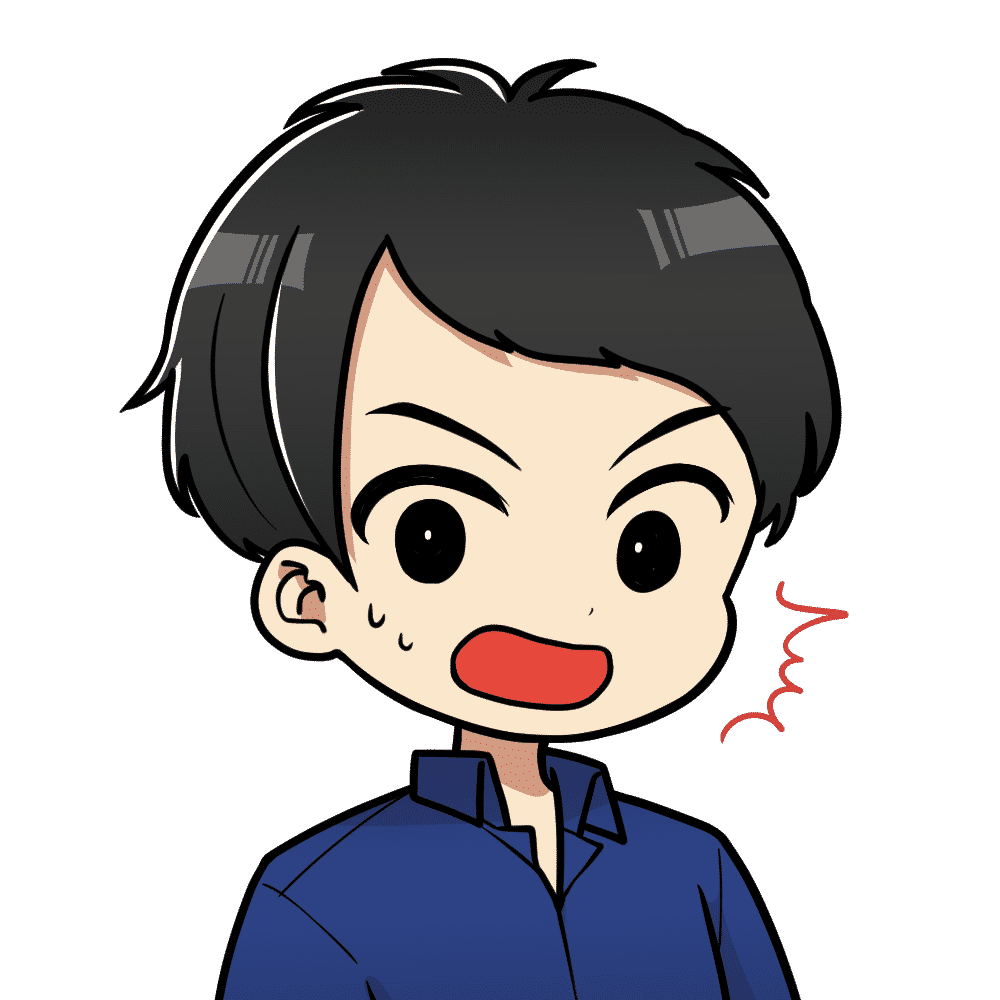
大卒のニート率が倍増以上なんですね・・・
コロナで大幅増加
令和3年3月に公示された、厚生労働省青少年雇用対策基本方針 によると、若年労働者の人口減にもかかわらず、ニート総数が平成27年〜令和元年まで50万人台で高止まり状態であると報告されています。
これは、暗に、ニート比率が高くなっているを示唆しています。
また、残念なことに、令和2年はコロナ禍の影響で前年比+13万人増加となり、ニート総数が69万人となりました。
大卒ニートの増加理由

先述のとおり、1990年代と比べて大学以上卒の割合が高くなっていることがわかりました。
それはなぜか?
厚生労働省はいくつかの仮説を立てています。
大学進学率の上昇
大学進学率は、昭和時代から今日に至るまで年々増加しています。
とりわけ1990年ごろから今日に至るまで、およそ1.3倍に増加しました。
つまり、大学卒業者の増加に比例して、ニートの大学卒も増加しているということです。
短期での離職率増加
3年以内離職率は、近年高止まりしており、2017年3月大学卒においては32.8%(※)に及んでいます。(※出典:厚生労働省)
一般的に、短期離職は再び正社員としての労働機会に失う傾向にあるため、後述しますがそのままフリーターやニートへの転じてしまう事例が多々見受けられます。
学生生活から職業生活への円滑な移行が出来ない学生
2000年代、および2010年前後に就職氷河期では、就業ができない課題も有り、一定数の未就業・未就学者の増加がありました。
一方、2010年代は就職率が大幅に改善しているものの、ニート率は高止まりしています。
学生生活から職業生活へ円滑な移行ができず、キャリア形成に課題をもつ学生が一定数存在しているのが実情です。
フリーター・ニート期間の長期化が、就業を難しくしている
今日の日本においては、未就業期間が長いほど、再就職が難しくなる傾向があります。
つまり、フリーター・ニート期間が長期化するほど、本人が就業希望であってもなかなか定職に就きづらい課題が生じます。
本人が未就業状態からの脱却を希望しても、そのハードルの高さに困難を感じ、就業を諦めるケースが存在します。

では、難関大学といわれる大学を卒業した「高学歴ニート」はなぜニートになるのか。
その背景についても、次項で考察してみましょう。
高学歴ニートは、なぜ「ニート化」したか
冒頭ですが、私の結論は「心身的な問題」、あるいは、「就業猶予期間の延長」だと解釈しています。
基本的にはその人自身はハイスペックであることも多いので、私の周囲の方々は数年のうちに就職します。
しかしながら、高学歴ニートを「ひと括り」に考えるのは危険な場合があります。
場合によっては、周囲のサポートが必要かもしれません。
本章では数通りの場合分けを考え、例を交えながらニート化の原因や脱出法を検討してみます。
- 本章の参考文献
- ・ニートの状態にある若年者の実態及び 支援策に関する調査研究 報告書
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/dl/h0628-1b.pdf
ケース1:精神的な疾患が原因にある場合
厚生労働省の調査によると、ニートのうちの約半数程度が、精神科・心療内科の受診歴があるとのことです。
このケースでは、ニート状態かどうかはあまり重要ではなく、まずは治療に専念するべきでしょう。
一方で、高学歴の方のうち、健康面でのコンディションが整わないことに失望し、より病状の悪化が懸念される場合があります。
現実の受け入れが難しいことが、特に高学歴の方には多いかも知れません。
この場合は、周囲のサポートが必要だと思います。
焦らないように、徐々に社会復帰していくための小さなステップを、少しずつ踏ませてあげる必要があるでしょう。
Dさんのケース
私の大学院時代の先輩であったDさん。
Dさんは優秀で、大学院に進み、博士過程に進みました。
しかし、博士課程二年になったころ、研究成果が出なかったことや採用試験にも落ちたことから、精神耗弱状態に陥ってしまい、徐々に研究室にも顔を出さないようになっていきました。
結局、その後は体調不良により、最終的には中退されることとなりました。
私もその後はなかなかお会いすることも叶わず、かろうじてFacebookを通じて交流があった程度ですが、寛解するまでは家で治療に専念されていたようです。
Dさんと少しお話できたのは、中退から5年後。
徐々に社会復帰に向けて歩み出しをされている、と伺いました。
Dさんは、「周囲や親にはとても感謝している。好きなようにやらせてもらえて、心がラクに感じた」とのことでした。
一時はかなり重度だったともおっしゃられていましたが、やはり精神疾患においてはまず治療に専念するべきで、無理をせず、周囲のサポートも得ながら、徐々にステップアップするしかないのだ、と感じました。
そんなDさんは、現在、塾講師として社会復帰されたとのことです。
ケース2:モラトリアムの延長
なにかやりたいことを追求するため、あるいは見つからないために、就業までの期間を猶予する人がいます。
以前、話題になった「林先生も驚く初耳学!」で紹介された高学歴ニートは、このケースに当てはまるでしょう。
そもそも、海外では「卒業後にすぐ就職しない」という選択肢はよくあることです。
私は外資系企業に在籍していますが、海外大学出身者は数年のモラトリアム期間を経て入社することも頻繁にあります。

日本だと、空白期間はダメ、と言われがちですが、米国や英国では卒業後すぐに就職しないケースが多々あります。
このパターンは、そもそも就職する前にしっかりと時間を作りたい人たちなので、正直言ってあまり気にする必要がないタイプと思っています。
現に、私の周辺にも、このケースの高学歴ニートは数名いますが、数年後にすんなり就職しました。
詳細の事例については、以下の記事にまとめていますので、是非ご一読いただければと思います。
本記事では、 ・有名難関大学を卒業した高学歴ニートのその後の人生 について、記述しています。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); メディアでは、たび[…]
ケース3:博士課程や専門大学院で年齢を重ねた場合
私は、高学歴ニートを語る上で、このケースが一番厄介だと考えています。
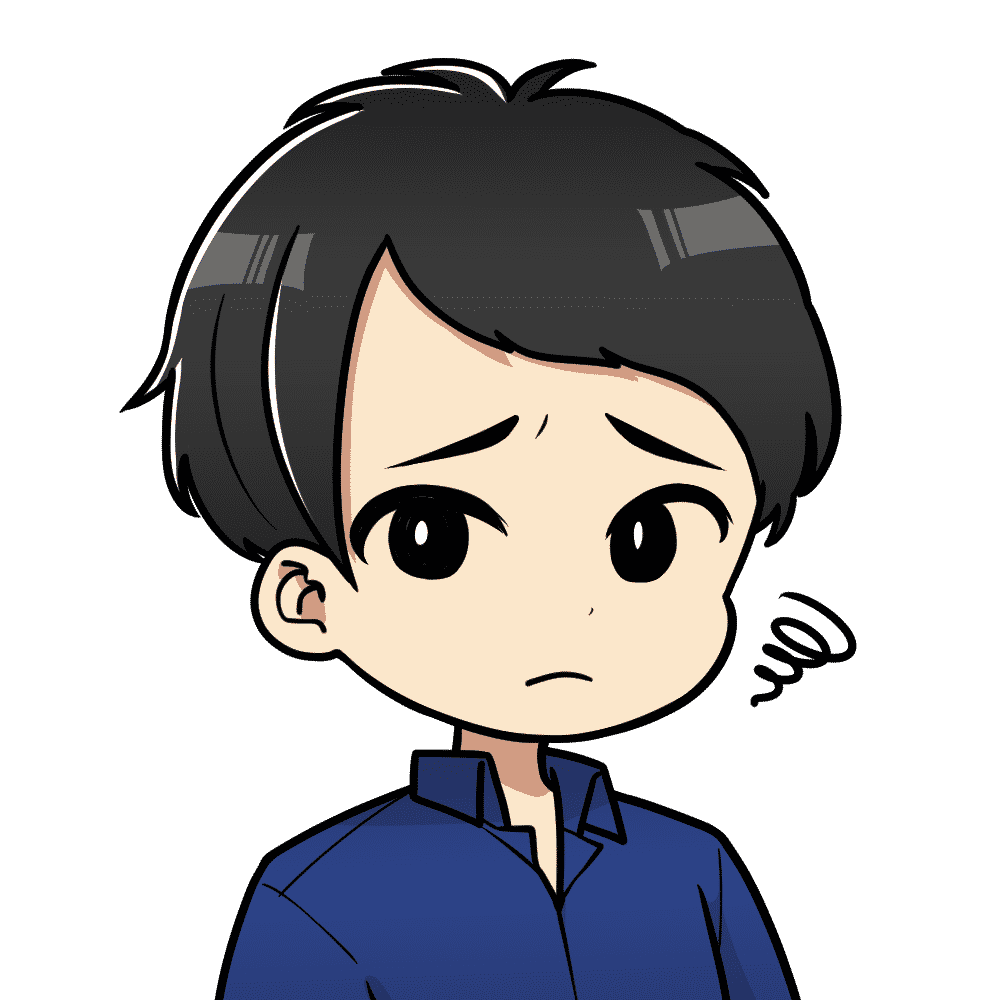
いわゆる「ポスドク問題」ですね。
私は理系大学院を修士で卒業していますが、例えばポスドク問題は身近に感じるところがありました。
- ポスドク:大学院の博士課程を終了後、任期付きの研究職のことを指します。いわゆる大学教員の登竜門的なポジションで、このポスドク期間を経て、助教以上の教職員になります。
- ポスドク問題:薄給かつ非正規職員であるため将来の保証もない。成果が出ないと教職員ポジションに就けないだけでなく、年齢を重ねているため民間企業も敬遠傾向がある。
Eさんのケース

Eさんは、東京大学 理科Ⅰ類に現役合格。その後の進振りで第一志望の工学部に入り、成績もトップクラスでした。大学院に進学後も教授の推薦もあり、博士後期課程へ進みます。
Eさん自体も、このまま教職員へと夢を膨らませていたようです。
しかしながら、大学教員は運の要素も有り、ポジションに空きがないと教職員になれません。Eさんが博士後期課程を修了後も結局空きがなく、機会を求めて西日本の片田舎にある大学でポスドクとして働き始めました。
夢破れ、就活で苦労
しかしながら、これもまた運。ポスドクは有期契約であるため、任期の間にポジションに空きがないと次に進めません。残念なことに、Eさんは民間への就職を余儀なくされてしまいました。
ここから、更に彼を追い詰めます。
その後1年ものあいだ、Eさんは就職活動を続けましたが、既に31歳という年齢や民間での就業経験がないことを理由に就活は困難を極めたのです。
この状況を見かねた古巣の東大の教授が、私の前職である外資系会社へ連絡し、「とりあえずインターンでいいから雇ってもらえないか」と依頼し、教授のコネにより彼は半年のインターン採用になります。このインターン雇用の条件は、好成績であれば正採用となる、と付されています。
正規採用ならず、再度ニート期間へ
しかしながら、ここで正規採用に至ることができず、再度未就学・未就業期間に突入です。
幸い、このインターン期間を民間就業期間としてカウントする民間企業に出会えたようで半年後には就職先が見つかったようですが、このように東京大学卒業であるEさんであっても、非常に苦労するケースが見られます。

このケースは他にもありますね。大学教員という大きな夢を追いかけている方にとって、現実の落差が大きい場合は心の整理にも時間がかかるように思います。
高学歴ニートがニートを脱出するために
基本的に高学歴ニートはスペックは高いものの、社会復帰のためのリハビリ期間を踏む必要があるかも知れません。
本章では、厚生労働省の調査結果を元にして、ご紹介します。
- 本章の参考文献
- ・ニートの状態にある若年者の実態及び 支援策に関する調査研究 報告書
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/dl/h0628-1b.pdf
精神的な状態を確認すること
厚生労働省のレポートによると、ニート状態にある方々のうちの一定数、精神耗弱状態にある可能性が想定できるとしています。また、発達障害の可能性の有無も確認したほうがいい場合もあると報告されています。精神的な状態等に瑕疵を感じる場合は、医療機関で確認されるべきです。
自己評価の向上に繋げるステップアップ
ニートの社会復帰の妨げになる最大の敵は「自己肯定感の低さ」と言われます。
まずは、継続してみること。徐々に仕事がこなせるようになれば、自信もついてきます。
この段階では、最初から無理をし過ぎないこと。挫折をしないこと、に重点を置かれるべきです。
生活リズムを整える
ニートの多くは、昼夜逆転の生活を送ったり、生活リズムが不規則になりがちです。
しっかりと一日のリズムを作らないと、就労意欲が継続できない場合があります。
日中は日光に浴びる、朝食はとる、など、規則正しい生活の定着から始めるとよいでしょう。
同時に、少し外出や運動を始めることで、仕事に必要な基礎体力もつけていくことも重要です。
コミュニケーションを取る
ニート状態にある場合、コミュニケーションする相手も限定的になりがちです。
そのため、少しずつ話し相手を広げていくことをやるといいでしょう。
機会が設けづらい部分があるかも知れませんが、例えば英会話や趣味サークルに入れば会話もできます。
もしそれもハードル高いのであれば、部屋で発声練習や話し方の練習などでもまずは始めることをおすすめします。
就職は「ニート」に強い就職支援サービスを利用すること!
会社によって、「未就業状態の既卒」を敬遠する場合もあれば、歓迎する会社もあります。
直接応募だと、その見分けが難しいと思います。
そのため、「ニート」案件も対応可能な就職支援サービスを利用するといいと思います。
以下、いくつかご紹介します。
 就職Shop
就職Shop
![]() 就職Shop は、リクルートが提供する就職支援サービスです。本サービスは、リクルートの他サービス(リクナビ等)とは異なり、就職相談を受けた上で求人を紹介する流れになります。
就職Shop は、リクルートが提供する就職支援サービスです。本サービスは、リクルートの他サービス(リクナビ等)とは異なり、就職相談を受けた上で求人を紹介する流れになります。
特徴も面白く、(1)書類選考がない求人を紹介している、(2)求人企業は100%取材済み、(3)内定者4人のうち3人は正社員未経験者、という特徴を持っています。そのため、既卒フリーター、ニートにも利用しやすい就職支援サービスであるというのがメリットだと思います。
 UZUZ
UZUZ
![]() UZUZ は、20代を対象としたフリータ・ニート向け就職支援サービスです。
UZUZ は、20代を対象としたフリータ・ニート向け就職支援サービスです。
UZUZの大きな特徴は、キャリアカウンセラー自体が第二新卒・フリータ・ニートなどを経験しているという点。つまり、求職者と同じ境遇を経験した方がキャリアカウンセラーになることにより、同じ目線でサポートができるという点は非常に強みだと思います。
また、ブラック企業は徹底的に排除しているため、求人の安全性も高い特徴があります。
 UZUZ 20代理系の就職サポート
UZUZ 20代理系の就職サポート
![]() UZUZ 20代理系の就職サポート は、20代の理系を対象にした就職支援サービスです。
UZUZ 20代理系の就職サポート は、20代の理系を対象にした就職支援サービスです。
先述のUZUZと同じ特徴に加え、本サービスでは理系求人、とりわけ情報分野・電気電子・機械系の求人を多数取り扱っています。
もし読者が理系出身で、技術職への就職を検討される場合は、![]() UZUZ 20代理系の就職サポートへ登録すると良いと思います。
UZUZ 20代理系の就職サポートへ登録すると良いと思います。
むすび
最後になりますが、個人的には「高学歴ニート」は基本的にハイスペックな人が多いので、なんだかんだと成功する人が多いんじゃないかな、という気がしています。
私が以前に書いた記事「高学歴ニート達は、大学卒業後どのような道を歩んだか」で紹介した3名の方もニート期間があるとは言え、今は全員成功しています。
また本記事で紹介した元・ポスドクのEさんも就職し、その後は優秀な技術者になっています。
少し精神的な疾患に苛まれたDさんにおいても、社会復帰までゆっくりと時間がかかりましたが、今は楽しそうに仕事をやっています。
私自身は、彼らの「モラトリアム期間」を設ける生き方に賛同し、羨ましくも感じます。長い人生、100年時代を生きる中で、少しばかりの就業猶予期間は、心のゆとりにも繋がりますしね。
私も願わくば、どこかで数年のニート期間を設けられるくらいにゆとりを持ちたいな、と淡い夢を描いているところです。